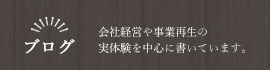はじめての中国1
2016.04.26
再生日誌
五陵年少金市東 五陵の年少 金市の東
銀鞍白馬度春風 銀鞍 白馬 春風を度る
落花踏盡遊何處 落花踏み盡くして何れの處にか遊ぶ
笑入胡姫酒肆中 笑って入る胡姫の酒肆の中
李白が飲んだくれながら詩を詠んでいた長安の都には、胡姫と呼ばれるイラン系のホステスがいる酒場が沢山あった。もちろん、女性ばかりでなく、当時の中国大陸には胡人のコロニーが無数にあり、特に河北地方には大量の胡人が住み着いていたことが近年の研究によって明らかになっている。イラン人というと、我々日本人は周辺のトルコ人やアラブ人とあまり区別がつかないが、言語学的にみるとインド=ヨーロッパ語族に属し、トルコ人やアラブ人よりもヨーロッパ人に近い。この時代に詠まれた詩の碧玉炅炅雙目瞳,黃金拳拳兩鬢紅といった表現からもわかるように、混血の進んだ現代のイラン人に比べて、唐時代の胡人達はよりプリミティブな印欧系の特徴を残していたようである。貴族の若者が銀の鞍を付けた白馬に乗って金髪碧眼の娘がいる酒場に向かう光景は、開元の治と称えられた華やかな国際都市長安の様子を良く伝えている。
しかし、どの時代、どの国でも、繁栄は永遠に続くものではない。繁栄はその頂点でそこはかとない腐臭が漂い始め、やがて急速に破局へと向かって行くことが多い。李白は想像もしなかったであろうが、繁栄を極めた長安の都も、1人の胡人が率いる反乱軍の馬蹄に踏みにじられることになる。反乱軍の虜囚となったもう一人の高名な詩人が変わり果てた長安の都を遠望し「国破山河在 城春草木深」と詠んだのは、白馬の若者が酒場へと急いだ繁栄の日々からわずか十数年後のことなのだ。その反乱自体は比較的早期に鎮圧されたが、大唐王朝は屋台骨に致命的な傷を受け、緩慢ではあるが避けようのない滅亡のプロセスへ踏み入っていくことになるのである。
私が初めて上海に行った時、浦東の新空港はまだなく、東京からの便は全て虹橋空港に着いた。虹橋空港も今はリニューアルして随分と綺麗になったが、当時は暗くて、汚くて、いかにも発展途上国の空港、といった風情だった。海外旅行が好きで随分色々な国に行ったが、中国には行ったことがなく、行きたいと思ったこともなかった。しかし、中国に子会社がある以上、行きたくなくても行かないわけにはいかない。私とS常務は、地方都市の空港からやってくるS社のY社長を虹橋空港で待っていた。日本から寧波への直行便はないので、寧波に行くには上海で寧波行のローカル便に乗り換えるのだ。
私は会社に入ると直ぐに、S社への貸付問題に手を付けた。その問題のために会計事務所を辞めたようなものだったから、なるべく早くけりをつけたかったのだ。私は支援などさっさと打ち切って、これ以上損が拡大しないほうが良いという意見だったが、我が社の経営陣、会長である祖父、祖父の弟の専務、社長の父は、事の重大性は認識していたものの、我が社の主力事業に密接に係っているS社が倒産することで、多額の貸倒損失が計上されるだけでなく、事業の遂行に甚大な悪影響が出るのではないかと恐れていた。当然、ラディカルな解決策には消極的だ。そしてS社との取引と中国子会社を管轄している量販部門のS常務は極めて楽観的だった。私がS社への貸付に対する見解を質すと、
「S社?全然大丈夫ですよ。一時は苦しかったけど、今は利益が出るようになってますから。決算書?当然もらってますよ。」
と言って、S社の決算社を見せた。売上高約5億円、経常利益3千5百万円、借入金2億円、債務超過でもない。売上高経常利益率7%は、藺草製品問屋にしては異常に高い。勘定内訳明細を見ると、なぜか我が社からの借入金がどこにも記載されておらず、借入金は全て地元の地銀からのものだった。しかも、借入金が2億円なのに、支払利息が3千万円以上計上されている。あからさまに不自然だ。その点を指摘すると、「私は数字疎いんで、Y社長に直接聞いてください。ちょうど今度一緒に寧波に行くことになっているから室長も一緒に行きましょう!」
ということになった(ちなみに、私の肩書は取締役社長室長だったので、社員から室長と呼ばれていた)。決算書の内容を聞くだけなら、わざわざ中国に行くまでもない。S社に行くなり、Y社長に来てもらうなりすれば良いのだ。1日で済む。今にして思うと、S常務はクレームを付けてきたバイヤーに対処するように私に対応したのだろう。日本に比べてアナーキーな中国に連れ出して接待すれば、大抵の問題は有耶無耶になるものだ。ようするに、S常務はS社の問題など、どうってことなく、入社したばかりで張り切っている私を適当にごまかせば済むと思っていたのである。当時、我が社は業界でも地域でも自他ともに認める優良企業だったから、経営者から新入社員まで、社内に危機感などまるでなかった。S常務だけでなく、経営者も、仕入担当者も、物流も、経理も、S社に何億円貸付ようが、前払いで何億円も仕入をしようが、数字の根拠は特になく、今日の繁栄は明日以降も永遠に続くと信じて疑わなかったのである。
なんで決算書の内容を聞くだけなのに中国まで行かなければならないんだとは思ったが、中国子会社を見ておくのも悪くないので、私はS常務と中国に行く事にし、私は虹橋空港の入国ゲートの前でY社長を待つことになったのである。
Y社長とは面識がないので、一応、事前に父にY社長はどんな人?と聞いておいた。
父の答えは、「Y か。Yはな、安禄山のような奴だ。」
だった。
あん ろくざん 【安禄山】
[705~757]中国唐代の武将。ソグド人。安史の乱の首謀者。玄宗皇帝に信頼されて平盧 (へいろ) ・范陽 (はんよう) ・河東の三節度使を兼任していたが、755年、反乱を起こして洛陽・長安を攻略。大燕皇帝を自称したが、子の慶緒 (けいしょ) に殺された。
(出典:デジタル大辞泉)
どんな人か、全然わからない。
父は非常に言語的なセンスに富んだ人なので、今にして思うと、その言葉にも色々な含意があったのだろうが、当時は役にたたない情報ばかり寄越しやがって、と思っただけだった。そんな情報だけでは、どうせ見分けられるわけがないと思いつつ、入国ゲートから出てくる日本人をぼーっと眺めていると、何と、いかにも安禄山、といった感じの男が出てきた。今入国ゲートから出てきた日本人の中から、安禄山に一番似た人を指させ、と言われれば、100人のうち90人までが、数人の従業員と思われる男を従え、太鼓腹を揺すりながらノシノシと歩くその男を指さすに違いない。それが安禄山ことY社長との初めての出会いだった。
初対面のY社長は実に愛想が良かった。どちらかというと、鷹揚、と言う表現が一番あっているかもしれない。まるで我が社からの借入など1銭もないかのように、やあやあ、よく来ましたね、といった感じで、握手を求めてきた。
30分ほどの短いフライトで寧波の空港に着くと、夜中にもかかわらず、10人ほどの従業員が迎えに来ていた。運転手と通訳はわかるが、ホテルに行くだけなのに、一体なんでそんな大人数で来る必要があるのか、少々驚いた。タイムチャージ制の会計事務所から転職したばかりだったので、こういう時間の使い方にどうにも馴染めなかったのだ。
出迎えの一行の中から「シャチョーサン」と若い女性の声がした時には驚きを通り越してギョッとした。なんと、もしかして10代ではないか?と疑うような幼い外見の女の子が混じっていたのだ。当時私はまだ若く、世慣れているとは言えなかったので、現地法人の事務員か何かだろうが、夜中に若い女の子を迎えに来させるとは非常識だ、と思ったのだ。迎えのマイクロバスに一行が乗り込むと、その女の子は当然のようにY社長の隣に座り、Y 社長は当然のように自分の娘より若そうなその女の子の肩に手を廻した。S常務も含め、周りの社員は何事もないように談笑している。
着く早々、心底うんざりした。
2016.04.26