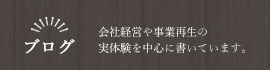中国と畳
2015.05.24
再生日誌
中国寧波市は、市区人口だけでも200万人を超える歴史のある古い町である。日本における一般的な知名度は決して高いとは言えないが、中国の歴史に詳しい人であれば、遣唐使が目指した港町、あるいは日明貿易の窓口として寧波の名前を聞いたことがあるかもしれない。しかし、寧波周辺が実は畳の原材料となる藺草の一大産地であることを知る人は、畳業界関係者以外、ほとんどいないに違いない。現在は大分変っているだろうが、私がはじめて寧波を訪れた2000年代のはじめは、寧波の市街から車を20分も走らせると、周りは一面藺草の田圃が広がっており、市内のホテルには畳業界の関係者と思われる日本人が屯していたものだった。
興味のない方は飛ばして読んでもらってかまわないが、少し畳業界について説明をしておきたい。
畳はあえて分類すると住宅建材に含まれ、さらに細かく分ければ床材の一種である。しかし、純然たる工業製品と言って良いカーペットやフローリングなどの床材と違い、畳は農産物としての特徴を色濃く残している。そのため、流通形態も特殊だ。通常の床材は一般的に大メーカーによって製造され市場に供給されているが、畳の場合、畳表を製造しているのは、「生産者」と言われる農家である。藺草農家は、藺草という農産物を栽培するだけでなく、それを畳表に織るまでを行っているのである。各農家が織った畳表を買い集めて製品化するのは、岡山、広島、福岡、熊本など昔の藺草産地(今では熊本以外ではほとんど藺草を栽培していない)にある「産地問屋」の役目である。産地問屋は畳業界の中で中核的な役割を果している業種であるが、最大手の問屋でも売上高は年間数十億、ほとんどの問屋は売上高数億円程度の規模である。産地問屋が生産者から集めた畳表は、日本全国にある「消費地問屋」に送られ、消費地問屋が町の畳屋に供給している。私の会社は関東でも最大手の消費地問屋だった。
日本の高度成長期には、藺草の需要も爆発的に伸び、業界全体が潤うことになった。工業製品である他の床材と違って藺草の生産は急に伸ばすことはできないので、経済学の原則に従って単価が上昇し、個々の藺草農家は笑いが止まらなかったろう。しかし、業界全体としては笑ってばかりはいられなかった。折しも生活様式の洋風化が進んでおり、供給不足が長引けば、床材としての畳離れに繋がる可能性もあるのだ。1970年代から80年代にかけて、一部の積極的な業者は、藺草の苗を携えて海の向こうに藺草の供給地を求めた。藺草は日本でしか栽培していなかったから、当に0からのスタートである。試行錯誤の末、日本の藺草産地である西日本と気候風土の似通った中国の江蘇省や浙江省で藺草の栽培が始まった。中国に進出した業者は織機を持ち込み、業界慣習から生産者以外長らく手を出せなった畳表の直接生産にも乗り出した。中国産畳による供給の増大は、進出した一部の業者だけでなく、市場規模の拡大を通じて業界全体を潤した。しかし、それも中国産畳の洪水のような流入が始まり、マーケットの秩序が失われるまでの短い間のことでしかなかったのである。初期に進出した業者は上手く供給をコントロールできると考えていたのだろうが、合弁として事業に参加しノウハウを積んだ中国の現地資本が独自の生産を開始していく経過は、アパレルや電子部品など他の業界とほぼ同じで、あっという間に市場は中国産畳に需要を奪われていくことになる。
私の会社は、消費地問屋として畳屋向けに畳を供給するだけでなく、GMSや1970年代の後半から急速に増加したホームセンター向けに上敷きといわれるゴザ(畳の上やフローリングの床に敷く、畳表を縫い合わせた敷物)を販売していた。ピーク時には100万畳以上を販売する東日本の上敷き販売では最大手であったが、これらの商品は通常の畳よりもさらに価格競争が激しく、1990年代になると、従来のように産地問屋から仕入れて販売するだけでは、いずれ立ち行かなくなることが明らかになりつつあった。そんな折、上敷きや藺草枕などの仕入先だったS社から合弁で中国に進出し、上敷きや藺草枕の生産を行うことを持ちかけられたのだ。
何事にも慎重な私の父は、この計画に大反対であったという。製造業のノウハウもなければ、海外で企業を経営するノウハウも経営資源もないから当然だ。しかし、当時社長をしていた祖父がS社の社長と私の会社のホームセンター向け部門の担当役員S常務に連れられて中国寧波に視察に行き、帰ってきた時には、既に中国に会社を設立する合弁契約書に署名していたそうである。かくして、祖父の独断により、投資計画も、資金計画も、生産計画も、利益計画も何もないまま、中国への進出が決定された。合弁比率は、当社6千万円、S社3千万円、中国合弁企業1千万円であったが、S社と中国企業は現物出資と労務提供で、金銭的な負担は全て私の会社が持つことになった。何せ他の合弁相手は資金が全くないので、私の会社が資本金以外にも貸付金として5千万円以上の金をつぎ込むことになったが、兎にも角にも数年で生産は開始され、中国現地法人自体は順調に動き出したかに見えた。
ところが、やがて、予想もしなかった資金負担が発生することになる。S社が資金を無心してきたのだ。表向きの理由は、中国に人を送り込むなど経営資源を投じているので、そちらに金がかかる、とのことだったが、不足資金の根拠は全く示されなかった。しかし、中国現地法人の運営は全てS社任せであり、S社が倒産すれば中国現地法人の経営も行き詰まることになるので、結局、S社に言われるがまま、年々貸付金や前渡金が膨れ上がり、私が会社に入る直前の決算では、S社への債権は2億円にも達していた。このS社への貸付問題を父に相談されたことが、私が会計事務所を辞めて実家の会社に入ることを決めた直接のきっかけとなったのである。
2015.05.24