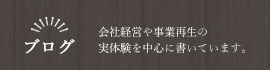相続対策の蹉跌
2019.01.03
再生日誌
鷲が死んだ。羽をもらいに行くとしよう。
神聖ローマ皇帝カール6世崩御直後の国際情勢の風刺
「シュレージエンを失うくらいなら、ペチコートを脱いだほうがマシよ。」
マリア・テレジア
ウィーンの宮廷で、プロイセンとの妥協を薦める廷臣達に
「犬どもよ、ずっと生きていたいのか?」
フリードリッヒ大王
コリンの戦場で、軍旗を手に軍の先頭に立ち、敗走寸前の自軍の兵士達に
自分の地位と財産を子孫に受け継がせたいと思うのは、古今東西、貴賤貧富に関らず変わらない人間の性であるが、受け継がせたいものが溢れんばかりにある人々のほうがその思いがより強いのは当然である。
ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール6世も、そんな人間の性に捕らわれた一人であるが、彼には娘しかいなかったので、他の王侯達に比べても取分け悩みが深かった。カロリング朝の系譜を引くヨーロッパ諸国では、古代ゲルマン法に起源を持つサリカ法と言われる法体系が存在しており、特に相続法に関しては近世までその影響が残っていた。サリカ法では女子に相続権がなく、一夫一妻制のキリスト教受容以後は、男子でも庶子には全くと言っていいほど相続権がなかったので、正妻が男子を生まなければルクセンブルク家やヤギェウォ家のような強力な家門ですら雲散霧消する運命にあったのである。
カール6世は、神聖ローマ皇帝、ベーメン王、ハンガリー王、オーストリア大公、その他星の数ほどある称号と先祖が戦争と婚姻によって掻集めた中欧一帯に広がる広大な領土を自らの子孫に受け継がせるべく、多大な努力を払った。彼は周辺国や世襲領の等族達に様々な政治的譲歩を行い、娘婿であるロートリンゲン公フランツ・シュテファンには先祖伝来の領土をフランスに譲り渡すことすらさせて、長女のマリア・テレジアへの世襲領の相続と娘婿の次期皇帝就任を列強や帝国選帝侯達に認めさせることに成功した。当時の神聖ローマ帝国の慣習からすれば画期的なことだ。彼の晩年は相続対策のために費やされたと言ってよい。
カール6世は自分の努力に満足して死んでいったかもしれないが、後世の歴史家達は彼の行ったことを無駄な努力の事例のように扱っている。
フランスは皇帝と何を約束したにせよ、ハプスブルク家を弱体化させる機会を逃すつもりは最初からなかったし、位を継いだばかりのプロイセン王フリードリッヒに至っては、大嫌いな父親が遺した皇帝との約束など眼中になく、その父親が遺した強力な軍隊を使って皇帝の娘から領土を奪い取ろうと考えていた。選帝侯達もあっさりと約束を違え、新しい皇帝にヴィッテルスバッハ家のカールを選んだ。無理もない。皇帝の娘と結婚するために由緒ある帝国封土をこともあろうに外国に譲り渡し、皇帝の婿という以外もはや帝国諸侯とすら言えなくなった青年に帝冠を載せるなど、そもそも気が進まないうえに、モルヴィッツの敗戦でハプスブルク家の軍隊がオイゲン公時代の精強さを失っていることがわかった以上、死んだ皇帝との約束を守る理由などあるはずもない。
マリア・テレジアが何かと反抗的なハンガリー等族達の支持を取り付け、フリードリッヒに奪われたシュレージエンを除くハプスブルク家世襲領を守り抜き、頼りない夫のために皇帝位を奪い返すことができたのは、彼女の優れた政治力とカリスマ性のおかげであった。彼女が凡庸な女性であったなら、ハプスブルク家は解体・消滅していたことだろう。
しかし、彼女の優れた政治手腕をもってしても、小国の王に過ぎないフリードリッヒからシュレージエンを奪い返すことはできなかった。300年来の宿敵フランスと手を組むことまでしてプロイセンを四面楚歌に追い込んだにもかかわらず、彼女の軍隊はフリードリッヒが父親から受継いだ精強な軍隊をどうしても決定的に打ち負かすことができなかったのである。
カール6世の努力が全く無駄であったとは思わないが、あてにならない列強や諸侯の約束を取り付けるために領地の割譲や政治的な譲歩を行うくらいであれば、カール6世はフリードリッヒの父親がそうしたように、強力な軍隊とそれを支える国力を育成して娘に遺すべきだったのだ。そうすれば、無理な外交に頼らずともハプスブルク家がシュレージエンを失うことはなかったに違いない。
オーナー経営者の特性として、少し事業が成長すると関連会社を沢山作りたがるという性癖がある。我が社にも本体である笠間商産の他に、幾つかの関連会社があった。その中の一つに笠間貿易という会社があり、我が社の海外仕入は全てその会社を通して行われていた。もちろん、わざわざ輸入業務を別会社でやる理由は何一つなく、笠間貿易を設立した真の理由は相続対策だった。会社を作って祖父の持っている持株の一部を移し、その会社で一定以上の規模の事業を行えば、その会社の相続税評価は類似会社比準方式で行うことができ、結果として祖父が亡くなった際の相続税を安くあげることができる。祖父は相続対策とかそういったことにはあまり興味がなかったように思うが(自分は不死身だと思っていた)、典型的なオーナー経営者であったので、当時の顧問会計事務所に勧められるままに喜んで新しい会社を設立した。問題は作った会社に何の事業をさせるかであったが、当時増えつつあった貿易業務でもやらせておけ、ということになったようである。
このようにして、売上規模5、6億円、売掛金が1、2億円あるそこそこの会社ができたのであるが、設立した目的が目的だけに、規模に相応しい管理体制を整えることには誰も無関心だった。かくして笠間貿易は、月次試算表もなく、我が社の経理課長が手書きの帳面を見ながら年1回の決算でバタバタと帳簿を締めるまで売掛金を初め各勘定がいくらあるのかもわからない個人事業水準の管理体制で経営されることになった。金融機関からの輸入跳ねの枠が2億円もあったにもかかわらずである。
販売先が笠間商産だけであったうちはそれでもよかったかもしれないが、他社にも販売を行うようになると、話は全く別である。それがS社のような本来与信できないような先であれば尚更だ。
輸入を行う場合、国内での仕入と違って、通常は代金を前払いするか、信用状(L/C)を銀行に発行してもらう必要がある。前払いをするには資金が必要であるし、L/Cの発行は銀行にとって与信行為なので、与信を受けられる財務体質がなければならない。中国子会社からの仕入の大部分は輸出ライセンスを持つ中国系商社を通して我が社が直接仕入れてS社に製造管理手数料を支払っていた。その分についてはS社は運転資金を必要としなかったが、枕や座布団など一部の商品は直接仕入れをせず、S社経由で仕入を行っていた。また、S社は我が社以外の主に関西を商圏とする問屋などに販売する商品も中国から仕入れる必要があった。資金力も信用もないS社は輸入の資金を笠間貿易に頼り、人の好い我が社の経営陣はさほど深く考えることもせず応じていたのである。
笠間貿易は銀行からL/Cと輸入当貸と呼ばれる貿易金融の枠を合計で2億円作ってもらっていた。当貸は通常は枠の範囲で出し入れ自由の借入なのであるが、輸入当貸の場合、予め仕入から一定期間を定めてその範囲内で返済することを条件にする場合が多い。我が社の場合、当貸の期間は4ヵ月で設定されていた。つまり、仕入れてから4ヵ月以内に商品を売って、代金まで回収すれば、月5千万円程度であれば輸入による資金繰りの悪化は発生しない仕組みとなっていた。S社からも4ヵ月以内に代金を回収さえすれば、例え利鞘はほとんどなかったとしても、問題は発生しないはずだった。
最初に異変を感じたのは、私が入社して数か月後、夏物の仕入が増え始める5月のことだった。当初考えていた資金繰りよりも3月、4月の笠間貿易への支払いが異常に多いのである。経理課長に聞くと、11月、12月の仕入れで借りた輸入当貸の決済資金を笠間貿易に送っている、とのことだったが、冬場でも上敷など一定量の藺草製品は売れるとしても、11月や12月に我が社分としてそんな多額の輸入はないはずだった。嫌な予感がして笠間貿易の試算表を見せてくれと言うと、決算の時に締めるだけで、試算表は作っていないという。昨年10月時点の直近決算書を見ると、S社への売掛金が5千万円、我が社への売掛金が5千万円、輸入当貸が1億円ほどあった。一見、あまり異常のないバランスだが、良く考えると、取引量がずっと大きい我が社への売掛金とS社への売掛金が同額なのはおかしい。案の定、昨年10月の時点で既にS社への売掛金は4ヵ月のサイトを超過していた。
S社への貸付金が最近増加していないカラクリがここにあった。S社から半年以上笠間貿易への入金はなく、夏物の仕入が始まった5月半ば時点で調べるとS社への売掛金は既に1億円を大きく超えていた。つまり、S社は代金を支払わずに輸入した商品を我が社に売りつけ、その代金はちゃっかり受取っていたのである。我が社から金を借りなくてもやっていけて当然だ。
慌ててS社向け商品の輸入を止めようとしたが、簡単にはいかなかった。既に量販店向けの夏物の商流は動き出しており、下手に混乱すると欠品を出し、得意先から取引停止になってしまう。量販部門からはとにかく今年の夏物商戦が終わるまで荒っぽいことはしないで欲しいと泣きつかれたし、実際問題としてS社が潰れて物流が止まれば、我が社の存亡に関わる。結局、毎日のようにS社の経理担当と連絡を取り、我が社自身の資金繰りとS社の資金繰りを睨めっこし、S社が潰れないぎりぎりのところで資金供給してなるべくS社への債権が増えないようにするのが精一杯だった。そして、夏物商戦が終わった時点で、笠間貿易のS社への売掛金は1憶8千万円にも達することになった。このことは、夏物の仕入に係る輸入当貸の決済をしなければならない年末にかけて、大幅な資金不足が発生することを意味していた。
父や祖父はS社への売掛金が延滞していることを知らせなかったことで経理課長を詰ったが、彼からすれば、我が社から笠間貿易に対する支払いは全て役員から印鑑をもらって行っていたことだし、笠間貿易での輸入当貸の決済も、書類を見せて役員から印鑑をもらっていたのだから、S社のために仕入れた商品代金を我が社の資金で決済していたことは父や祖父も解っていたはずだ、との理屈になる。彼は自分の役割は資金を必要なところに必要だけ流すだけであって、それ以上のことは経営者の仕事と考えていたし、課長というポジションからすれば、そう考えて当然であろう。
財務に疎いことを理由にして経営者が財務的な問題の責任を逃れることはできない。だがもし、笠間貿易がなく、我が社が直接輸入業務を行っていたら、S社への売掛金が滞っていることは直ぐに発覚し、もっと早く手を打つことができただろう。我が社では売掛金はシステム管理されており、遅延の発生を経営陣は毎月のデータで直ぐに確認することができたからである。経営陣が財務に疎いことをカバーするために、我が社はお金をかけて管理システムを整えていたのだ。ところが、笠間貿易という管理の行き届かない会社が挟まったことによって、危機を認識することができなかった。
会社オーナーにとって、相続対策(現代ではもっと狭義に相続税対策を言うことが多いが)は確かに必要かもしれない。しかし、肝心の相続すべき事業を変に歪めてしまうような対策であればやらないほうが良い。古今東西、最高の相続対策は、相続する対象を強力な状態で後継者に渡すことだ。それさえできれば、後は何とかなるのである。
2019.01.03